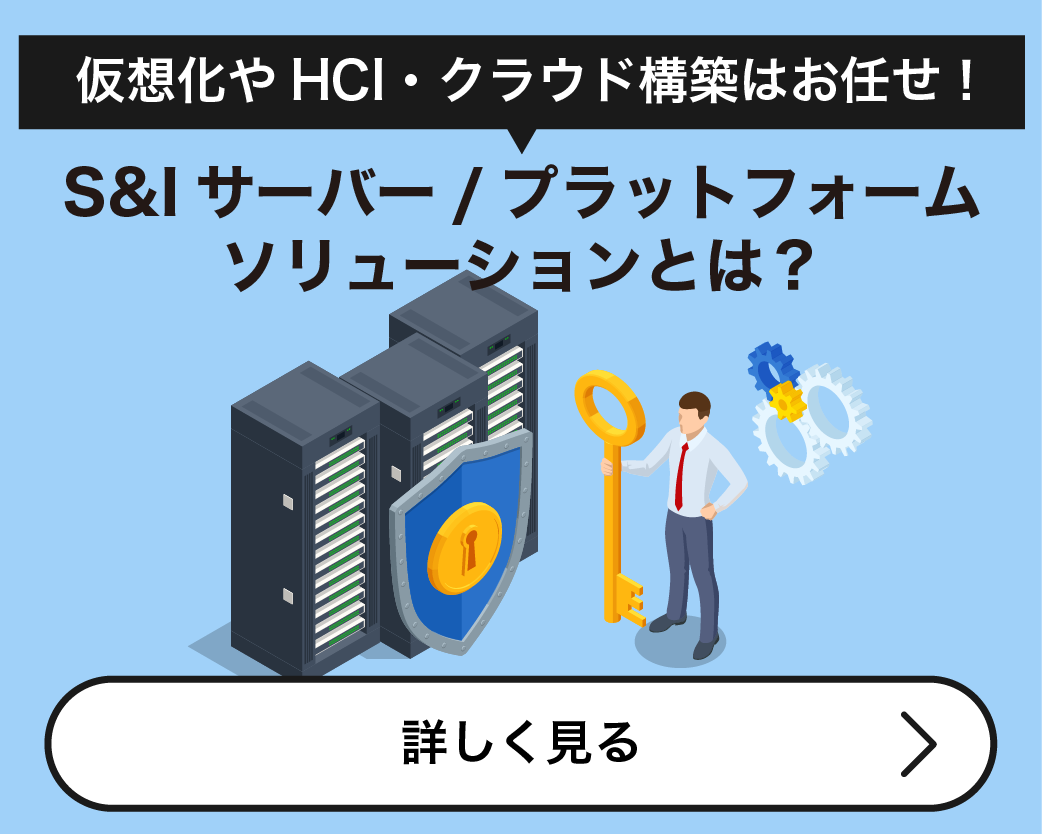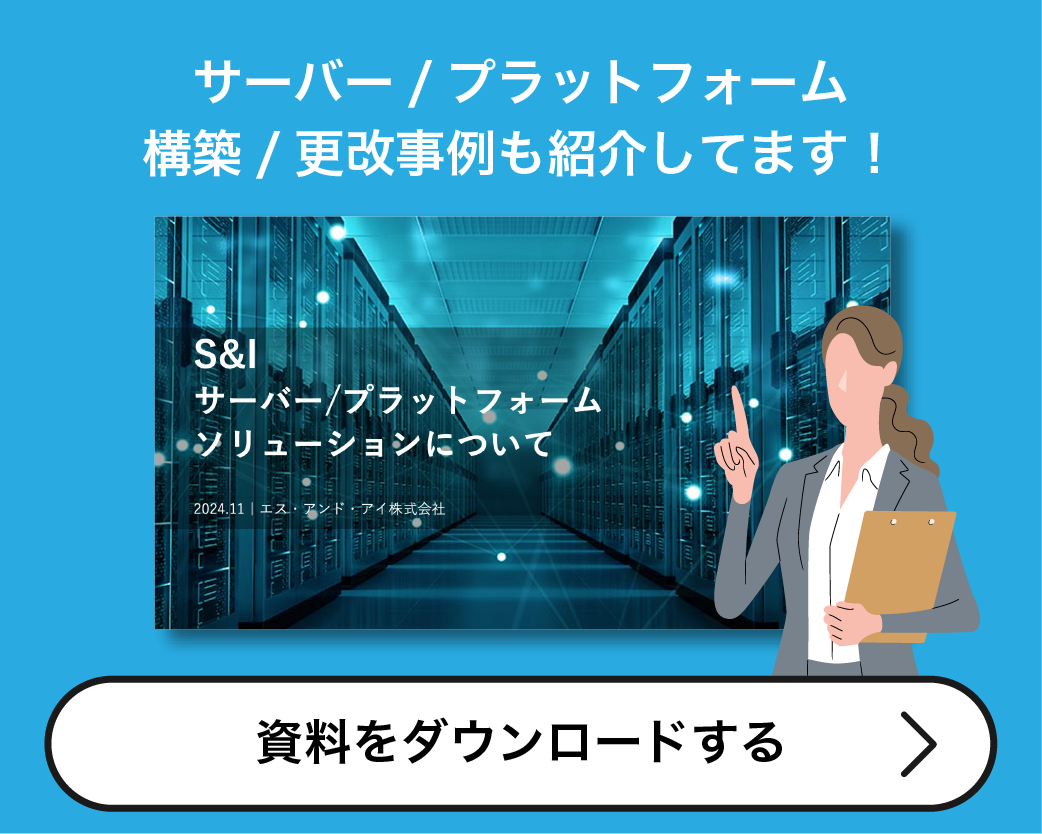事例の紹介に入る前に、改めてVxRailのサポート体制について整理しておきましょう。
VxRailは、DellがVMwareと共同設計したHCI(ハイパーコンバージドインフラストラクチャー)製品で、ハードウェアとソフトウェアが一体となったソリューションです。
通常、仮想基盤では、サーバーはA社、ストレージはB社、仮想化はC社というようにサポートを提供するベンダーが異なるため、障害が発生した際に、ストレージなのか?サーバーなのか?仮想化層なのか?と原因を切り分けなければなりません。さらに、異なるベンダーにそれぞれ問い合わせる必要があるため、原因が分からないまま、たらい回しになることも少なくありません。一方で、VxRailのようなHCI製品は、ハードウェアとソフトウェアを単一ベンダーで一括サポートしてくれるため、障害発生時の複雑さが軽減できます。
特に、VxRailの場合はハードウェア・ソフトウェアの窓口が一本化されており、ハード・ソフトのどちらで障害が発生した場合でも問い合わせを行えばDell側でハードかソフトかを切り分けた上で適切な担当を割り当ててくれます。問い合わせのたびに部門間や製品担当をたらい回しにされることがなく、一貫したサポート体制のもとで、安心して運用が可能です。
また、バージョンアップの自動化やライフサイクルの一元管理ができる点もハードとソフトが一体となったHCI製品ならではと言えるでしょう。
構成変更時やトラブル発生時にも構成の整合性を簡単にチェックでき、トラブル対応が効率的に行えるほか、バージョンアップのワークフロー化・自動化により、日々の運用負担を大幅に軽減できます。
VxRailは、こうしたHCI製品の利点に加え、DellがVxRail全体を責任持って対応してくれる点が、より安心感につながっています。特に、VMwareの買収以降に導入された新たなVAO契約により、サブスクライセンスの全範囲にまでサポート対象が拡大されており、これまで以上に安心して運用できるサポート体制が整っています。