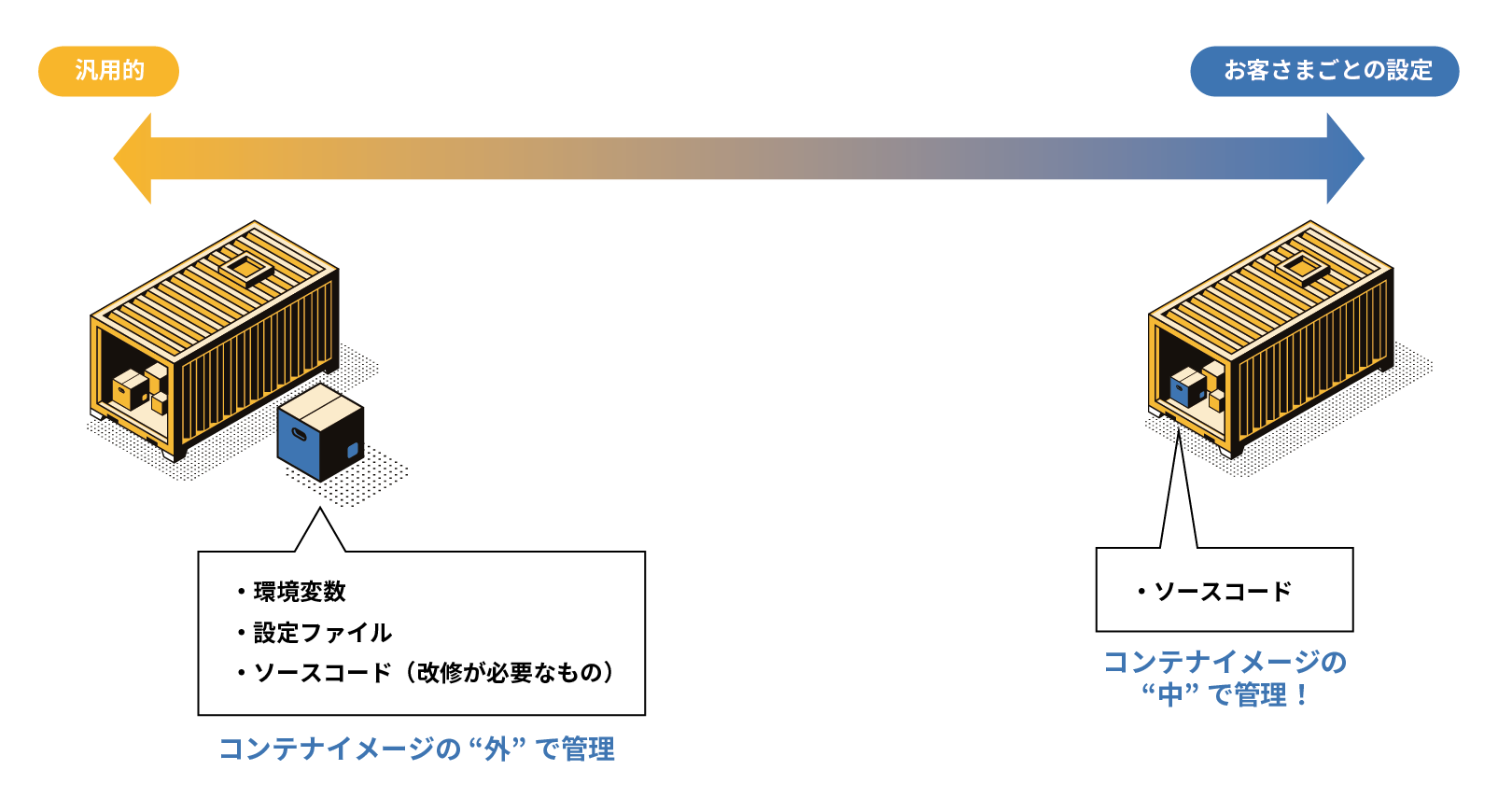少数のコンテナに集約できるようなアプリケーションで完結する、つまり単純なシステムの場合は、Kubernetesではなく、Docker/Docker Compose環境でも問題ないかもしれません。一方、多数のコンテナを必要とするサービスやマルチテナントを実現したい、スケールアウト/スケールインを頻繁に行いたい場合などは、Kubernetes環境が向いています。今回検証対象としたAI Digは、顧客を増やしていくためにマルチテナント化したい、という課題があったことから、Kubernetes環境 / OpenShift環境でのコンテナ化を目指しました。
Docker/Docker Compose環境、Kubernetes環境、OpenShift環境、いずれの環境の場合でも、コンテナ化するにあたって検討すべきポイントは変わりません。今回は、コンテナ化する際の検討フェーズ〜コンテナイメージの方針確定までをご紹介します!